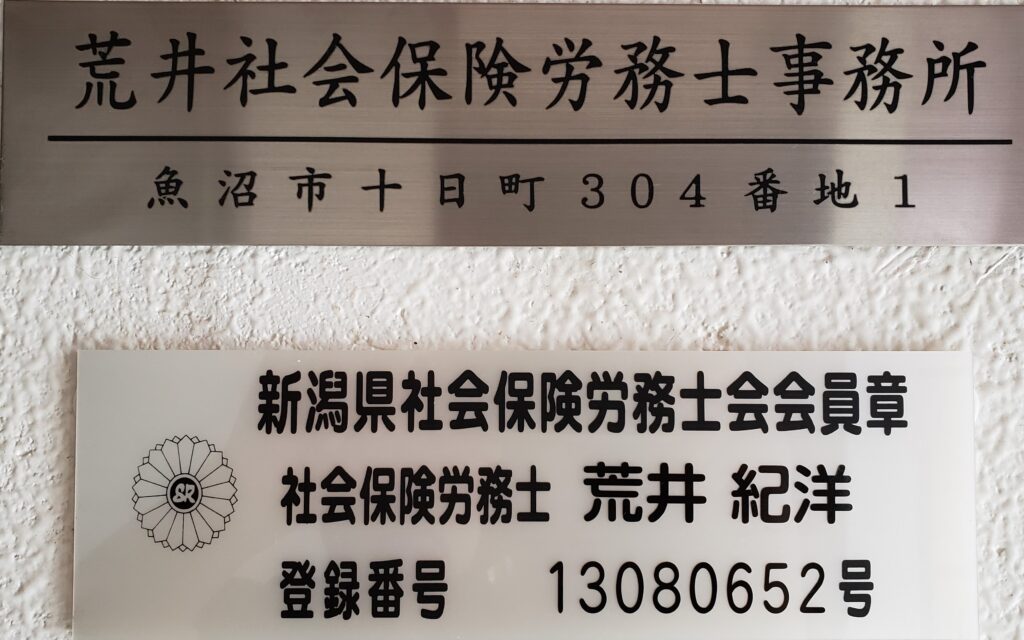労働時間短縮・年休促進支援コース
申請手続きのポイント
・ 交付申請時点で、常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、労働基準法第39条第7項に基づき、 時季指定の対象となる労働者の範囲および時季指定の方法等を就業規則に記載する必要があります(就業規則は各労働 者の年次有給休暇5日取得義務に対応していることが必要です)。
・ 常時10人未満の労働者を使用する対象事業場においては、労働基準法施行規則第24条の7に基づく時季、日数およ び基準日を明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成していることでも足ります(就業規則で規定されている場合も 対象です)。
・ 交付申請期限は2024年11月29日までとされていますが、予算の都合により締切り期限が早まる場合があります。
・ 2023 年度までは、「自己取引の禁止」として、提出代行や事務代理を行う社会保険労務士は助成対象の経費の支出先に なることができませんでした。2024年度から改正され、提出代行や事務代理を行う社会保険労務士も助成対象の経費の支 出先として以下の取り組みができるようになりました。ただし、必ず相見積もりが必要となります。顧問契約を結んでいる先だか らといった理由で相見積もりを取らずに契約の相手方とすることはできません。
1. 労務管理担当者に対する研修
2. 労働者に対する研修、周知・啓発
3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
5. 人材確保に向けた取り組み ・ 両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)との併給は可能です。
特別休暇は有給である必要があり、現在無給の休 暇がある場合は有給の休暇にすることも成果目標にできます。
・ 上限額の引き上げのための賃金加算については、最低賃金上昇時に行っても問題ありません。また、業務改善助成金の 賃金引上げ対象と重複しても問題ありません。
・ 交付決定前に取り組みに関する行為はできません。見積もりの取得までとなります。 ・ 労働時間等設定改善委員会等の議事録提出が必要であり、ひな形の提出は禁止されています。各事業場の実態に合わせ て討議する必要があり、開催時の写真の提出も求められます。Zoom等のWEB会議でも問題ありませんが、メールやチャット 等の文字だけの開催では要件を満たせません。
・ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新については、時間・工数の改善等具体的な指標で導入の必要性がわか る必要があります。