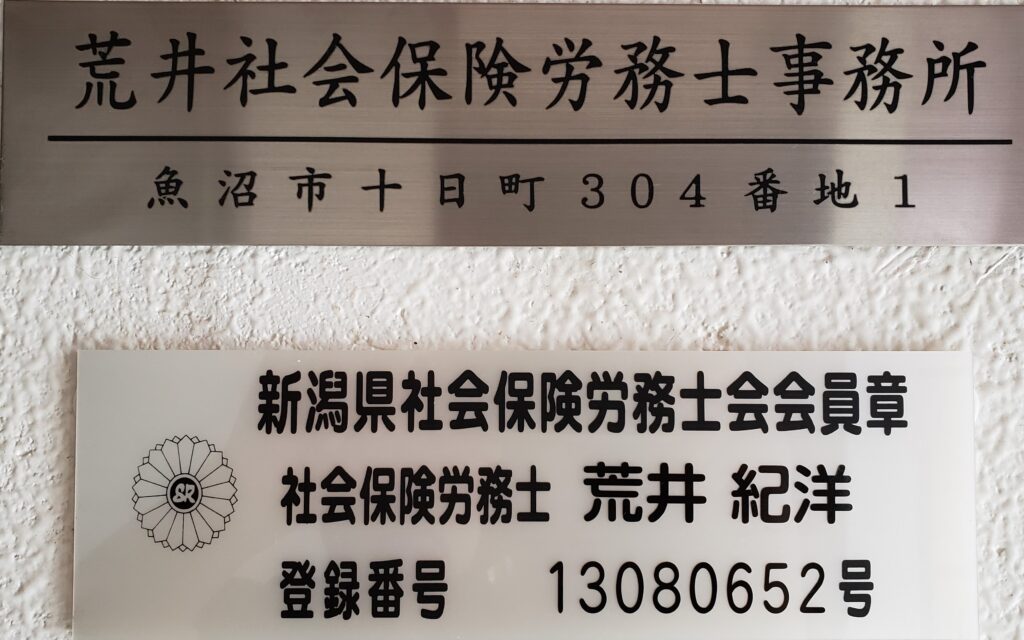受給のポイント
Facebook
Twitter
LinkedIn
- ① 育児休業取得の場合は、1人目は、連続5日以上が条件で す。そのうち所定労働日が4日以上なければなりません。
- なお、育児休業日数は、暦日ベース(休日等を含む)でカウ ントします。
- 期間中に表の右に記載している所定労働日数が 含まれていることが必要です。
- 休日等は就業規則やシフト表等 で確認されます。 2人目は連続10日以上、3人目は連続14日以上必要です。
- 詳しくは表を確認してください。
- ② 育児休業は育児介護休業規定等で定める必要があります。
- 最低でも厚生労働省の定めるモデル育児介護休業規定の簡易版 程度の規定である必要があります。
- 育児・介護休業等に関する規則の規定例≫≫https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
- ③ 当該休業等期間を有給扱いにする等、法律を上回る措置を行う場合でも、規定化されている必要があります。
- ④ 雇用環境の整備に関する措置を最低2つ以上
- (労使協定により出生時育児休業の申出期間を、2週間前を超えるものとして いる事業主は最低3つ以上)
- 行う必要があります。具体的な措置のうち実施しやすいのは下記の4つです。
- 雇用環境の整備に関する措置は次のとおり。
- a. 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
- b. 育児休業に関する相談体制の整備
- c. 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集・提供
- d. 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知
- ⑤ 就業規則等において、育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに関する規定を定め、
- 当該規定に基づき業務体制 の整備を行っている必要があります。
- 規定には育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項および引継ぎ対象業務の見直 しの検討
- に関する事項が含まれている必要があります。
- ⑥ 第1種は育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請をする必要があります。
- ⑦ 同一の労働者の同一の育児休業については育児休業等支援コースと併給調整がかかります。
- ⑧ 一般事業主行動計画の策定や一般事業主行動計画策定届の労働局への届出が必要です。
- 一般事業主行動計画の周知には 厚生労働省が運営する、
- 仕事と家庭の両立支援についての取り組みを紹介するWEBサイト「両立支援のひろば」が活用できます。
- ⑨ 令和3年度までに出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)を受給した事業主も対象になります。
- ⑩ 令和6年12 月17 日の支給要領改正により第2種の助成金を第1種の助成金を支給申請しなくても受給できるようになりまし た。ただし、第2種を先に受給した場合は、第1種は支給申請できなくなります。
-
。
- オープンなコミュニケーション: 社員間や部門間でオープンで率直なコミュニケーションを促進しましょう。意見交換やフィードバックを積極的に行うことで、信頼感や協力関係を築くことができます。
チームビルディング活動: チームビルディング活動や社内イベントを定期的に行うことで、社員同士の結束を高めることができます。楽しいイベントやアクティビティを通じて、共通の目標や興味を共有しましょう。
フレキシブルな働き方の尊重: 社員のワークライフバランスを尊重し、フレキシブルな働き方を促進しましょう。柔軟な勤務時間やリモートワークの導入など、社員が自身の生活に合わせて働ける環境を提供しましょう。
感謝と認定の文化: 社員の成果や貢献を適切に評価し、感謝と認定の文化を醸成しましょう。定期的な表彰や賞与、感謝の言葉などを通じて、社員が自己成長を実感し、モチベーションを高めることができます。
ダイバーシティとインクルージョンの推進: 社内における多様性と包摂性を重視し、全ての社員が自身のアイデンティティやバックグラウンドを誇りに思える環境を作りましょう。ダイバーシティを尊重し、インクルーシブな意思決定を行うことで、社員の多様な視点やアイデアを活かすことができます。
これらの要素を取り入れることで、社内の雰囲気を良くし、生産性やチームのパフォーマンスを向上させることができます。
- オープンなコミュニケーション: 社員間や部門間でオープンで率直なコミュニケーションを促進しましょう。意見交換やフィードバックを積極的に行うことで、信頼感や協力関係を築くことができます。