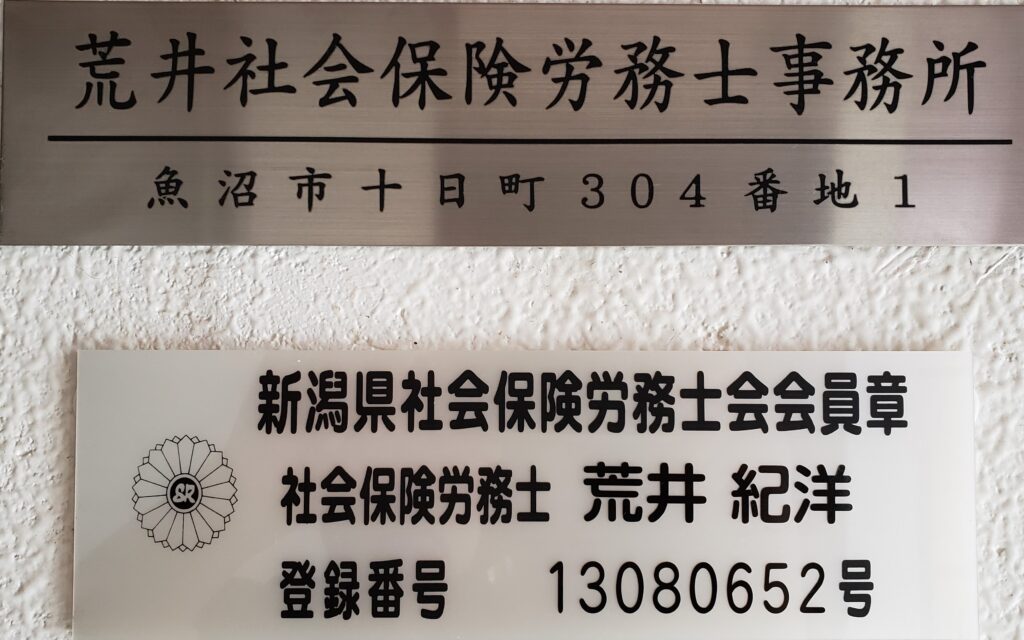就業規則(育児・介護休業規程)の見直しなどはお済みですか
- いわゆる令和6年改正育児・介護休業法が改正されます(令和7年4月1日・同年10月1日)。
- この改正に伴い、就業規則(育児・介護休業規程)・社内様式の見直しや、
- 個別周知・意向確認などの準備が必要となります。
- どのような改正規定があるのか? 今一度、確認しておきましょう。
□ 子の看護休暇の見直し ◆
□ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 ◆
□ 育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 ◆
□ 育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加 ◆
□ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化 ◆
□ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化 ◆
□ 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け ★
□ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数:1,000人超の企業→300人超の企業)
<令和7年10月1日施行分>
□ 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化 ◆
□ 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け ★
□ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け ★
注.◆が付いた改正規定は、厚生労働省のモデル規則(育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版])において、
改定が行われているもの。
注.★が付いた改正規定は、厚生労働省のモデル規則において、改定が行われているほか、
厚生労働省から「育児・介護休業等に関する規則の規定例」が
公表されています。
その規定例を見てみたい、見てみたが自社用にどのようにアレンジすればよいのか分からな
いなど、
この改正への対応にお困りの場合は、気軽にお声掛けください。
-
。
- オープンなコミュニケーション: 社員間や部門間でオープンで率直なコミュニケーションを促進しましょう。意見交換やフィードバックを積極的に行うことで、信頼感や協力関係を築くことができます。
チームビルディング活動: チームビルディング活動や社内イベントを定期的に行うことで、社員同士の結束を高めることができます。楽しいイベントやアクティビティを通じて、共通の目標や興味を共有しましょう。
フレキシブルな働き方の尊重: 社員のワークライフバランスを尊重し、フレキシブルな働き方を促進しましょう。柔軟な勤務時間やリモートワークの導入など、社員が自身の生活に合わせて働ける環境を提供しましょう。
感謝と認定の文化: 社員の成果や貢献を適切に評価し、感謝と認定の文化を醸成しましょう。定期的な表彰や賞与、感謝の言葉などを通じて、社員が自己成長を実感し、モチベーションを高めることができます。
ダイバーシティとインクルージョンの推進: 社内における多様性と包摂性を重視し、全ての社員が自身のアイデンティティやバックグラウンドを誇りに思える環境を作りましょう。ダイバーシティを尊重し、インクルーシブな意思決定を行うことで、社員の多様な視点やアイデアを活かすことができます。
これらの要素を取り入れることで、社内の雰囲気を良くし、生産性やチームのパフォーマンスを向上させることができます。
- オープンなコミュニケーション: 社員間や部門間でオープンで率直なコミュニケーションを促進しましょう。意見交換やフィードバックを積極的に行うことで、信頼感や協力関係を築くことができます。
就業規則(育児・介護休業規程)の見直しなどはお済みですか
-
- オープンなコミュニケーション: 社員間や部門間でオープンで率直なコミュニケーションを促進しましょう。意見交換やフィードバックを積極的に行うことで、信頼感や協力関係を築くことができます。
チームビルディング活動: チームビルディング活動や社内イベントを定期的に行うことで、社員同士の結束を高めることができます。楽しいイベントやアクティビティを通じて、共通の目標や興味を共有しましょう。
フレキシブルな働き方の尊重: 社員のワークライフバランスを尊重し、フレキシブルな働き方を促進しましょう。柔軟な勤務時間やリモートワークの導入など、社員が自身の生活に合わせて働ける環境を提供しましょう。
感謝と認定の文化: 社員の成果や貢献を適切に評価し、感謝と認定の文化を醸成しましょう。定期的な表彰や賞与、感謝の言葉などを通じて、社員が自己成長を実感し、モチベーションを高めることができます。
ダイバーシティとインクルージョンの推進: 社内における多様性と包摂性を重視し、全ての社員が自身のアイデンティティやバックグラウンドを誇りに思える環境を作りましょう。ダイバーシティを尊重し、インクルーシブな意思決定を行うことで、社員の多様な視点やアイデアを活かすことができます。
これらの要素を取り入れることで、社内の雰囲気を良くし、生産性やチームのパフォーマンスを向上させることができます。
- オープンなコミュニケーション: 社員間や部門間でオープンで率直なコミュニケーションを促進しましょう。意見交換やフィードバックを積極的に行うことで、信頼感や協力関係を築くことができます。