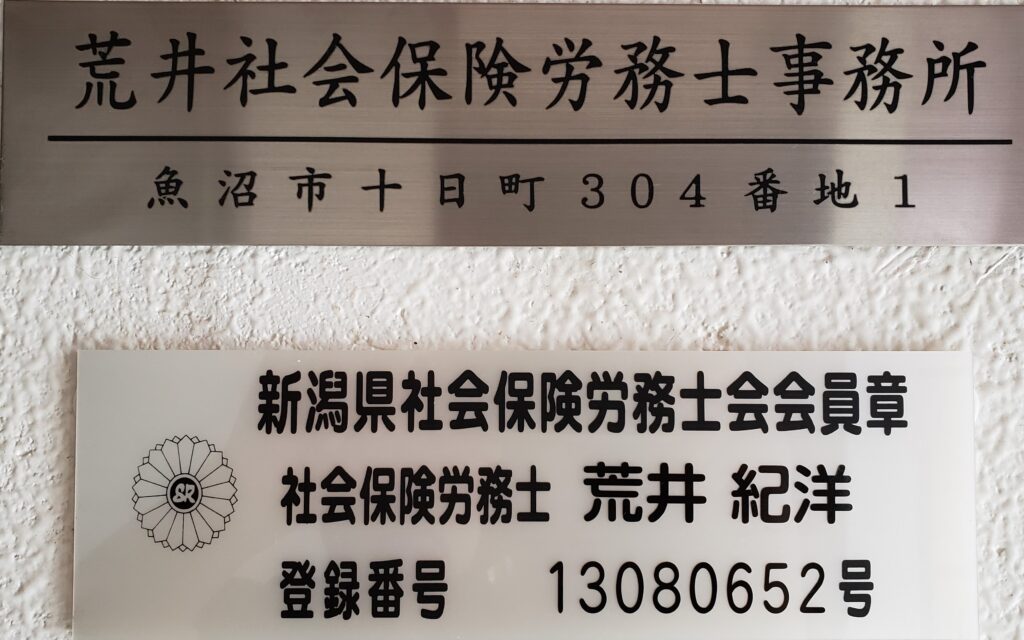不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
Facebook
Twitter
LinkedIn
- 受給のポイント
- 今回、参考として添付したモデル規程案では、各課題に応じた制度を整備したとして作成しています。
- ●不妊治療については、月 2 日まで取得可能な不妊治療休暇(無給・有給)、時差出勤や短時間勤務、
- テレワークの 活用、さらには業務内容や勤務場所の一時的見直しにまで踏み込んでおり、きめ細かい内容としました。
- ●月経に関しては、有給の生理休暇(月 2 日)や、PMS・PMDD 等への柔軟な勤務対応、
- フレックス制やテレワークの 導入が盛り込まれており、通常の年次有給休暇とは別に、女性が安心して体調に応じた働き方を選べる内容になっていま す。
- ●更年期についても、月 1 日の支援休暇や柔軟な勤務制度、職務・配置の一時的見直しなどが網羅されており、現場で の導入がしやすい構成となっています。 ただし、あくまでも規程案なので、自社に応じた日数や休暇を無給・有給にするかを含めて検討してください。
- 制度の運用において留意すべき点としては、まず既存の年次有給休暇や労基法上の生理休暇とは別に新たな制度として
- 就業規則や規程に明文化する必要があることです。
- 助成金の支給対象外とならないためには、従来制度の流用ではなく、 明確な区別が求められます。
- また、支援制度が実際に利用されたことを証明するための記録(申請書、勤怠記録等) も整備・保管しておく必要があります。
- 実務的な対応としては申出書等を準備することになります。
- さらに、不妊治療など個 人のプライバシーに関わる情報を取り扱う際には、
- 情報管理体制を整え、必要に応じて診断書を求める運用とすることで、
- 制度の信頼性を確保することが大切です。他の制度でも本人の申し出に基づく制度利用とし、
- 状況によれば診断書の提出 は不要とすることが重要です。 。